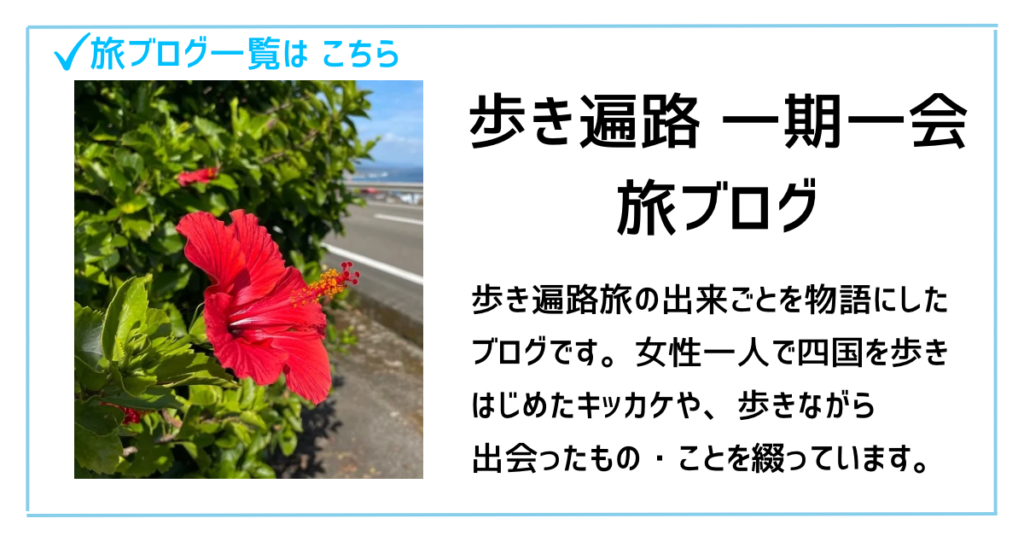どうしよう。
どうしよう、っていうか、どうした私。
自分の感情とは無関係に涙があふれてくるなんて初めてだ。
こんなことになるつもりで来たわけじゃないのに。
どうして泣いているのか、分からない。
どうすれば涙が止まるのかも分からず、立ちつくすことしかできないでいる。
四国の寺には行くのに、お墓参りに行った記憶がほとんどない
私は、身近な「死」から遠ざけられて生きてきた。
いや、遠ざけられた、なんて誰かのせいにしてはいけない、私が蔑ろにしてきたんだと思う。
じいちゃんも、ばあちゃんも。
むかし家にいたゴールデンレトリーバーも。
「この前、亡くなって葬儀まで終わったばい」
この世にいなくなったのを知るのは、いつも全てが終わった後だった。
親から事後報告の様に聞かされるたび「なんで!?」と驚いた。
「試験に響くといかんと思ったけん、言わんかったと」その都度いろんな理由を両親から聞いた。
「あんたのため、だったと」なんて言われてしまったら、私はそれ以上何も言い返せなかった。
そんなことが何度かあるうちに、「近しい誰かが、いつの間にかもうこの世にいない」ことは私にとっての普通となり、感情が動かなくなっていた。
墓参りの記憶は、一度しかない。
10年ほど前だったか、ばあちゃんの法事ということで、両親に車で寺に連れて行ってもらったから、墓がある場所も知らない。
2度目の墓参りを思い立ったのは、四国を歩き遍路したことがきっかけだった。
1,200キロともいわれる巡礼の道で、山の麓にある寺にたどり着いた時、急にばあちゃんの法事を思い出した。
だって、同じだったから。
あの時お参りした寺も、山の麓にあった。
墓がある九州と四国は、私が今住んでいる東京より近いんだから、ついでに墓参りに行ってみようかな。
軽い気持ちが芽生えた。
四国と九州が近いとはいえ、調べてみたら夜行バスと電車を乗り継いで11時間かかる。
親に一言「墓参り行ってくる」と言っておこうか迷った。
でも、言えなかった。
これまで、身近な人たちの最期に駆けつけなかっただけでなく、墓参りすら1度しか行った記憶がない。
そんな風に生きてしまった私は、親とこの話題について向き合える勇気がなかった。
墓の場所は、10年前に母が教えてくれた寺の名前だけが頼りだった。
名前だけでなく、漢字の書き方も教えてくれてたおかげで、記憶に残っていた。
とはいっても、10年前である。
もし間違えて覚えていたら、これから11時間かけて別の場所にたどり着くことになる。
でも、それでもいいと思った。
この思いつきを逃したら、次はいつになるか分からない。
11時間かけ、たどり着いた先で……
遍路旅の格好のまま、夜行バスに飛び乗った。
情けない話だけど、夜行バスの中で納骨堂の墓参りの仕方を必死に調べた。
でも、お寺によって納骨堂の様子が違うらしく、はっきりした正解がわからないまま、寺に着いてしまった。
道すがら、誰ともすれ違わなかったし境内にも誰もいなかった。
納骨堂に入れてもらうには、お寺の人に頼まなければならなさそうだけど、この寺の納骨堂で合っているのか確信が持てない。
大きなお堂の前で、いい年して右往左往した。
竹箒を持った女性が建物から出てきたので、怪しげな動きをやめて、勇気を出して話しかけた。
父の名を伝えると、すぐに中に案内してもらえた。
本当にここで合っていた。
納骨堂に通されて「ごゆっくり」と、ひとりになる。
一つだけ出されていた位牌を目にしたとき、なぜか10年ぶりに会うばあちゃんのだと分かった。
ひんやりとした空気が包む空間で。
ゆっくりお参りどころか、予期せぬ事態に焦り始めることになる。
いきなりだった。
涙があふれてきたのは。
え!?
慌てて首に巻いていたタオルで目元をおさえたが、あとから後からあふれてこようとする。
感動の涙でも、悲しみの涙でもない。
どうした私!?
すると、まるで他人事の様に冷静なままの心が、私に警告する。
ワンワン泣いている姿をお寺の人に見られたらどうするのか、と。
ここに案内してくれた女性は、父の名前を言ったらすんなり通してくれたし、その反応は父を「知って」いた。
「泣いていましたよ」なんて後で両親に言われでもしたらと思うと、焦りだした。
この涙の理由で、思い当たる節は一つ。
これまでロクに墓参りにも来ず、顔も見せなかったから、ご先祖様の怒りに触れたのだろうか。
いや……違う。
霊感など全く持ち合わせていないから、全然説得力なんてないんだけれど。
子供の頃、ばあちゃん家に遊びに行くたび、ばあちゃんは「よく来たね、よく来たねぇ」と嬉しそうに頭を撫でてくれた。
しわしわで、優しかったあの手ののひら。
涙が流れるばかりで言葉にならなかった思いを心で想いながら、立ちつくすことしかできなかった。
「ご両親、いつもお二人で熱心にいらっしゃっていますよ」
納骨堂を出ると、案内してくださった女性からがお話をしてくれた。
そんなこと、初めて知った。
納骨堂にビールとまんじゅうの形をした蝋燭があったのを思い出す。
きっと両親が供えたのだろう。
ここには、私が知らない両親の姿しかないことに、驚きと、寂しさが胸を覆っていく。
離れて暮らす20年は、決して短い時間ではなかったと思わずにはいられなかった。
ここ数年、正月の数日くらいしか実家で過ごしていない。
思えば、一緒に過ごす時間の問題だけではなく、話すこともしていなかった。
住職さんもきてくださって話を聞きながら、いくら家族とはいえ、これでは知らない人も同然になっていないかと考えさせられた。
墓参りのことにしても、私が勝手に気まずさを感じていただけで、そもそも話そうとしていなかった。
なかなか会えなくったって、話す手段も機会も、いくらでもあったのに。
納骨堂の前に立って、「たぶん、ばあちゃんがあの頃と同じように頭を撫でてくれている」ように感じたけど、お互いの言葉はもう届かなかった。
届かなくても、「ごめんね」の言葉はきっと聞いてくれていると、矛盾を抱えながら勝手に信じることしかできなかった。
子供だったあの頃とは、もう違う。
両親に、「墓参りに行きたい」と言えていれば、一緒に何度もここに来れていたであろう。
過ぎた日は戻らない。
そんな当たり前のことに気づかされながら、両親との残りの時間を大切にしよう、と思うのだった。
「墓参りに行ってきた」
実家に顔を出した私は、恐る恐る母に伝えた。
たったそれだけの言葉だったけど、これまで話すことをしていなかった私にはすごく勇気がいることだった。
「……ちゃんと包んでいったとね?」と聞かれ、思わず固まっていると「そぎゃんことも知らんかったんね」と怒られた。
今年は、一緒に墓参りに行けるときに帰省して、私が知らない祖父母の話を聞いてみようと心に決めたのだった。
歩き遍路道中でのできごとを綴った、旅ブログ一覧はこちらから。